「アルジャーノンに花束を」は何回もドラマ化や映画化がされています。
原作小説がテーマとする深さから読書感想文のテーマに選ぶ人も多い名作です。
映画やドラマも参考にできるので読書感想文の題材選びにオススメです!
読書感想文が書きやすい最適な理由や、作者が伝えたい事も考察します。
「アルジャーノンに花束を」が読書感想文にオススメな理由
「アルジャーノンに花束を」は小説が有名ですが、何回もドラマ化や映画化されている名作。
長期の休みになるとやってくる読書感想文にも最適なんです。
なかなか、小説を読んで書くのは進まない…
と言うときにも、映像が頭にあると入りやすいんです。
ドラマや映画は主軸は同じなのですが、主人公の名前が違っていたりします。
今回、一番馴染みある原作に合わせた呼び名に統一して記事を書いています。
チャーリーの感情の変化や成長がつかみやすい!
知的障害がある主人公のチャーリイは手術により知能や感情、人間性が変化します。
知能が上がるとき、上がりきった時、その後の低下…と、時間の進みにそって描かれています。
しかし、ただ客観的に物語が進むのではありません。
チャーリイー自身の感情の変化や考え方の変化がリアル。
それに伴って人間関係に現れてくる変化も描かれています。
知能による現実的な変化…など、見方一つで色々な考察や感想が浮かんできます!
客観的・主観的どちらからも深い考察、人とは違った一言を加えることができる作品なんです。
感情だけでなく倫理や道徳的なテーマを扱っている
チャーリイーの悩みに対しての感情や思考の動きだけの物語じゃないところが深いんです。善悪では語り切れない、倫理的な部分にも問題提起されています。実際の障害をもとに脳の手術や実験の考察による現実の動きも描かれています。科学技術が進歩して、不可能が可能になった時、そこにあるのは喜びなのか?
という問いかけがあります。
全てを標準律とするような思想によって本来の状態に人が手を加えていくこと。
それによって得られる喜びもあれば失われる何かもある。
本当の幸せはどれなんだろう。と考えずにはいられない。
その感想こそが唯一無二になるんです。
時代や場所を超えたわかりやすいテーマ
知能があがれば幸福度は上がるのだろうか?
自己を認識しはじめたことで、他者との違い、関係性などに悩みができます。。
チャーリィーにとって悩みであったことが解決したと同時に新たに複雑な悩みがでてきます。
知能が上がったり下がったりするにつれて、チャーリィーは多様な感情を味わい経験します。
「自分と他人」によって浮き彫りになる悩みは、誰でもが同じように思い悩むことでもあります。
悩みの本質に語りかけるストーリーには誰しもが自分の悩みに近いと感じるのではないでしょうか?
それだけに、多くの人が共感しやすい問題提起がしやすいんです。
読み解かなくても変化がわかりやすい構成
「アルジャーノンに花束を」は、チャーリイーの日記形式で進みます。
チャーリイーの手術前後、更にその後…と、
知能の変化が語られるだけでなく文章の変化としても表現されています。
リアルに変化する様子が描かれているので、客観的な語り口調の物語よりも印象に強く残ります!
通常、読書感想文は原作小説オンリーで書きだすことが多いですよね。
「アルジャーノンに花束を」は小説も有名ですが、何回もドラマ化や映画化されています。
つまり、文字からの印象だけでなく映像から受け取るイメージも加えられます。
いろんな洞察が得られるという点でもぴったりなんです。
私は、難しい言い回しはほとんどないのに考えさせられる深い物語だと思いました。
読み終わった後、誰しもがチャーリイーの幸せを考えると思うんです。
それだけ、感情移入が深い物語なんですよね。
「アルジャーノンに花束を」考察ポイント!見るべき…
つぎは『アルジャーノンに花束を』を観る時に考察したポイントです。
私が実際にどんなところに注目して、どう考察したか、まとめています。
主人公チャーリイの成長と変化
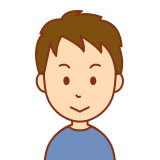
チャーリイの変化に注目。
知能が向上していく過程でのチャーリィーの感情や葛藤を考察。
チャーリイーの知能があがったのは結局一時的なものでした。
効果を「一時的」にしたことで、どんな意味があったのか?を考察してみました。
『一時的』だったからこそ、人間の幸せや尊厳、倫理観を考えさせられたんだと思います。
チャーリイが自分の変化を受け入れていくとき、知能の状態によって感情や変化も違っていました。
今までとは違った、「学べる」という高揚感と自分の可能性。
反面、感性のままに「感謝や幸福」を感じられなくなっていく心。
2極端ともいえる対比が見事なんですよね。
頭がよくなるって羨ましいと思ったけど、良いばかりでもないのかもしれない。
始めて、そう思ったときに、私の固定概念は外れました。
内側で自分を苦しめる優劣は結局のところ自分で決めていただけなのかもしれません。
作者が、一番言いたかったことは障害を治す可能性や条件つきの幸せについてではないと思うのです。
その人に与えられたすべてが、本来の、「その人自身」の生き方になる。
幸せは、何かと比べて決めるものではないし、どの側面を見るかで全く違う現実を作り出します。
チャーリイーに条件を付けた幸福の過程と、無条件の過程。
2つを対比させることで、より深く私たちの心に訴えかけてくるように思います。
科学技術の進歩と倫理的な問題
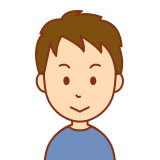
科学技術の進歩と、人としての尊厳、倫理的な問題を考察。
脳の手術という科学によって知能があがり助けられたと思いきや…
チャーリーはどんどん苦しそうに孤独になっていきます。
科学の可能性は素晴らしいと称賛しつつ、あるがままとはどういうことなのか?
人は人にどこまで介入していいのだろうか?
チャーリイーという人間への尊厳から見た時、ぶち当たる壁でした。
チャーリイーの幸せはどこにあるのだろうか?
私たちの多くは、どちらかしか味わったことのないことです。
単純なようでいて、とても難しい問題だと思いました。
結局のところ、ボーダーラインに明確な答えなどでない…。
それもまた、1つの答えなのかもしれませんね。
アルジャーノンとチャーリイーの関係性
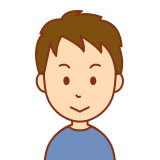
ネズミのアルジャーノンとチャーリイの関係性をタイトルから考察しました。
タイトルになっているのはチャーリーの最後の言葉です。
自分の知能が退化していく中で、最後のお願い。
それは、自分を忘れないで…ではなく、アルジャーノンへの弔いでした。
しかし、その中に私は、弔い以上のものも感じたんです。
同じ感覚を共有した友人としてのアルジャーノンへの労わりの言葉でもあると思いました。
アルジャーノンとチャーリイーは一心同体のような感覚だったんでしょうね。
自分と全く同じ環境を経験したアルジャーノンをただのネズミとは思えなかったのでしょう。
アルジャーノンはチャーリイーにとって、
同志であり親友であり家族、そして自分自身でもあったのでしょうね。
「アルジャーノンに花束を」で一番印象に残った名言
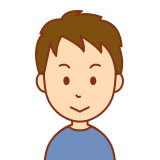
「アルジャーノンに花束を」で、一番印象に残ったシーンを考察しました。
チャーリーは最後に
どうかどうか、ついでがあれば
「アルジャーノンのお墓に花を供えてください」
と言葉を書き残します。
自分の知能が退化していく最後のお願い。
この一文に切なさが溢れました。
なぜかといえば、そこに、本来のチャーリイーを感じたから。
チャーリーは最後の最後に「自分」と言う幸せを取り戻す決意をしたのかな?と感じました。
チャーリーイにとって知能が上がると。世界は全く変わってしまいました。
さらには、退行することへの恐怖。
頭がよかった分、理解できていた分、余計に怖かっただろうと思うんです。
どちらかと言うと不幸な感覚に吞まれてしまったようにも見えました。
しかし、退行は進み、全てを受け入れていくチャーリー。
最後にチャーリーが願ったのは自分の事ではなかったんです。
同志であり親友であり家族でも会ったアルジャーノンに想いを向けていました。
チャーリイーは自分の一番大切なものが、再び見えはじめたのかもしれません。
温かさをちゃんと感じて、そして「自分」を取り戻したのだと信じたい。
チャーリイーの最後の言葉に、そう願わずにいられませんでした。
「アルジャーノンに花束を」に込められた意味。気付いたこと。
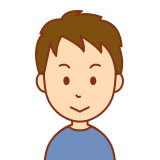
人の幸せとはどこにあるのか?。
与えられたもので何をするか?
という問いかけが込められているように思います。
「アルジャーノンに花束を」は、科学による人の希望や可能性も描いています。
同時に、人としての尊厳や幸福論がどこにあるかも投げかけていますよね。
知能があがること人が幸せになることは決してイコールではない。
という表面的な問題だけではないと思いました。
人にはすべてにおいて「与えられたものがある」
その点においては平等だと思うのです。
知能が横並びになることが平等ではない。
そして、幸せも人それぞれに与えられている。
そんなメッセージも込められているように感じました。
人はその「与えられたもの」を全力で使って生きること。
どんな世界を描き、どんな世界を創造して生きるのか。
といった本質的な答えのようにも感じます。
私は、チャーリーイの行動や変化をみたとき、
自分が「自分の世界」を作っている
ということを痛感させられました。
表面的な皮をはがしたとき
青い鳥のように、皆が想像できる『良いな』は表層の幸せだと気付くかもしれません。
人間の幸せは
「自分という与えられたものを最大限に生かす」
と言う中にこそあるのかもしれません。
「アルジャーノンに花束を」小説、映画、ドラマの違いと感想。
「アルジャーノンに花束を」は原作の小説、映画、ドラマと様々に流用されています。
それぞれ観てみると、結構違いを感じました。
小説はベースとなるので前章までの考察で省略します。
映画
2006年公開のフランス映画です。
95分のフィルムにまとめられているので、物足りない感じがありました。
知的障害があるため母親から疎んじられ、施設で育ったシャルル。学校の清掃夫として働いていた彼に、ある日チャンスが訪れる。新しく開発された薬によって知能の向上が可能だという。すでにネズミを使った実験に成功、次なる人間への実験にシャルルが選ばれた。やがて驚くべき早さで高い知能を獲得したシャルルは数学、生物学で論文を提出、音楽にも才能を示す。ところが、新薬による知能改善は一時的なものにしかすぎなかった…。引用元Amazon
チャーリイーではなく、シャルルと言う名前で登場します。
手術ではなく新薬というのも違いますね。
一番の違いは「退行の過程が薄い」こと。
性格が変化していく盛り上がり部分は強調して描かれています。
その分、最後の『一番、伝えたい事と答え』ともいえる部分がアッサリ終わってしまった感じ。
ドラマ
ユースケサンタマリアさんが演じたバージョンと、山下智久さん主演バージョンとあります。
個人的な感想にはなりますが、
原作のイメージと、伝えたかったことを、もっとわかりやすく映像にしてくれてるのは
ユースケ・サンタマリアさん主演のアルジャーノンかなと言う気がしました。
その後の変化が希望的なもので少し先の部分のようなイメージで描かれてます。
「人間の幸せ」「人間の尊厳」「成長」
それらの問いかけに対しての、1つの答えを表現してくれているように思います。
今回は、少し切り口を変えて紹介してみました。
「アルジャーノンに花束を」は見る世代によって感じ方が違います。
小学生、中学生、大人…
しかし、どの世代でみても、私たちの経験する悩みと本当は一番近い部分の物語に思えるんです。
「アルジャーノンに花束を」と言う物語は、各国でドラマや映画などにリメイクされています。
それだけ、愛されるのは、まさに人間の本質的な問いかけだからだと思うんです。
自分に幸せを感じられない時、
自分の輪郭をはっきり取り戻すことができるような素晴らしい物語だと思います。
是非、読む方も、観る方も、楽しんでくださいね。
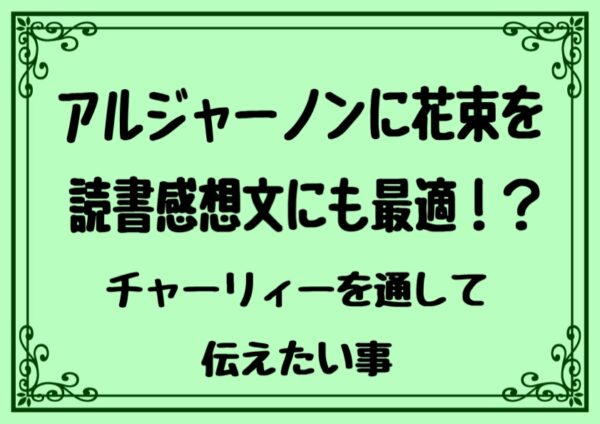
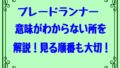
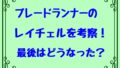
コメント